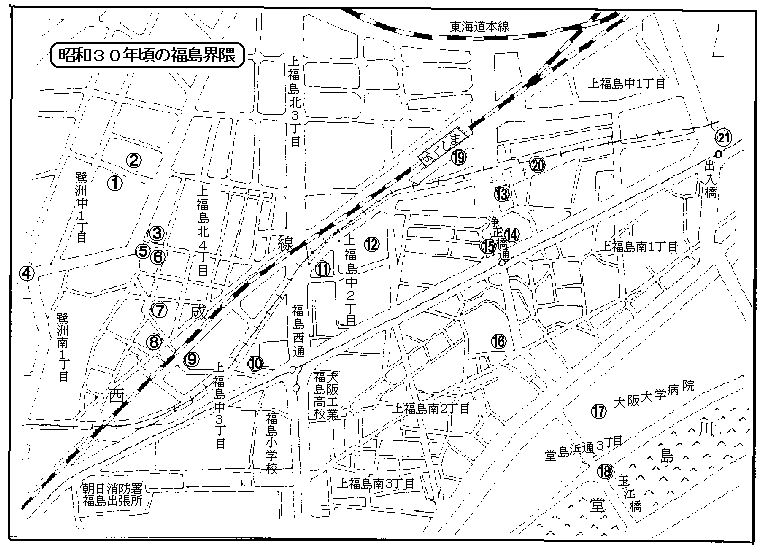 地図(拡大図)
地図(拡大図)
○ガード
少し行くと今度は阪神電車のガードの闇がある。ガードと言っても盛り土の下を掘り下げ、潜り抜けできるようにしたものである。かなり急な坂に掘り下げてある。闇の上を電車が通過する時の音を指で耳栓をしていた。道中の難所で、しょっちゅう水が浸き、ここでコース変更もあった。この轟音を響かせるガードの闇は、怖いながらも楽しい場所だった。
○停留所
ガードを潜り抜けるともう市電の電車道だった。そこで景観が変わった。すぐ右手にタイル張りの汚い公衆便所(⑩)がある。そこは福島西通りの交叉点である。ここは見知らぬ世界への玄関口でもある。お寺参りや時たま動物園に出かけたりする出発点である。ここには、天王寺動物園へ行ったり、天王寺さんにお参りしたりする時に乗る市電の福島西通という停留所がある。私は祖父(明治一九年生)から数えて三代目の大阪者である。身寄りを亡くした祖父は少年時代、丹波(兵庫県氷上郡朝坂村)の農村を出郷した。墓のない者たちは、浄土宗・一心寺にお骨を収める。祖父のオコツもそうした。それでできた骨仏をお彼岸には拝みに行った。その時は百済車庫行きであったかに乗った。
○市電の鉄橋の先
市電は、福島小学校、中の天神さんの跡地、洋館建の河原田医院の前を通って堂島大橋に向けて行く。堂島大橋の鉄橋までは、福島西通りあたりからでも眺められた。中の天神さんは空襲でやられて石垣だけがあった。市電はそこで左にカーブして見えなくなる。いつも市電が鉄橋を渡って小さく消えていくのを眺めていた。橋から先は、未知の世界である。市電は阿弥陀池筋を南に進む。心は逸る。「土佐堀」「京町堀」「白髪橋」「阿弥陀池」とやらの停留所の名前の意味はわからなかったが、憶えている。その日は車窓から存分に大阪の市街を見物できた。一番胸をワクワクさせたのは、高架になる所だった。太鼓屋の太鼓正のある芦原橋あたりであったか。その頃の大阪のマチには幾筋もの川があって橋が架かっていた。
○ボイラー置き場
一行は福島西通りの交叉点を、左(北)に曲り、阪神の踏み切りに向けて進む。その手前の空き地(⑪)に大きなボイラーが転がされていて、隠れん坊の場所だった。ボイラーの中は暗かった。この頃は、土管とか鉄管とかがそこらじゅうに転がっていて子供たちの恰好の遊び場所であった。物陰や闇は、怖い反面、ワクワクさせる空間であった。
○公園
右(東)に行くと、ラカンサンの公園(⑫)に差し掛かる。ここにはコンクリートでできた長く湾曲したベンチだとか、水飲み場とかがあった。ここで子守り役の祖母は、長いキセルを出して刻みタバコを一服吸っていた。このラカンサンの公園は、後で知ったことだが、五百羅漢が祀られていた所であり、明治の頃、焼き場・火葬場があった所らしい。上方落語の「長屋の花見」に出てくる貧乏長屋は、一説によればこの付近らしい。菱形に歪んだ家などは当時、もうなかった。この公園の長く湾曲したベンチは、珍しかった。
○裏通り
ラカンサンの公園を抜けて阪神線の踏み切りに出る。踏切を渡らずに細い道をまっすぐ東に行く。このあたりは、ちょっと怖い所と教えられていた。プロレスの力道山がいると大人たちから聞かされていた。もしかすれば組関係の人の事務所があったのかも知れない。力道山は「外人」をやっつける「日本人レスラー」でカッコよかったが、怖い人でもあった。このうらぶれた通りを抜けると、賑やかな浄正橋筋に出る。ここで景観がガラッと変わる。
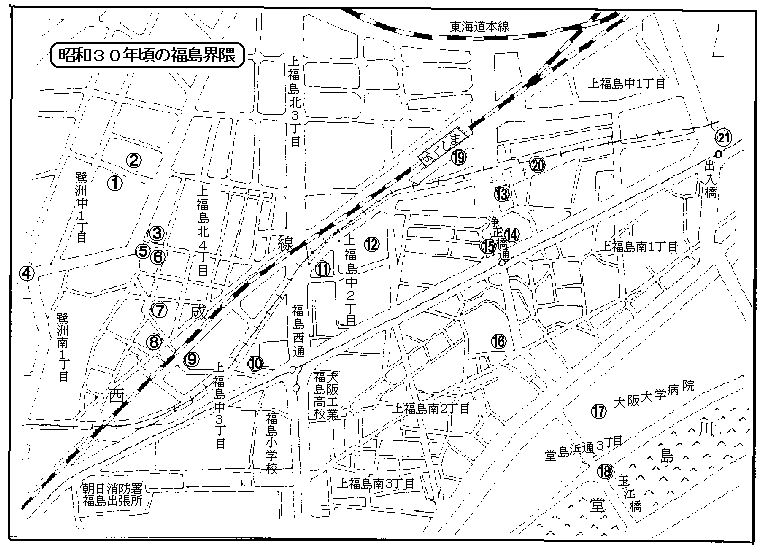 地図(拡大図)
地図(拡大図)